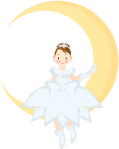
リフレイン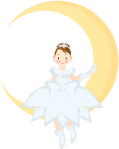
また、会えた。
澄みきった朝の大気に蔭る
あの樹の元に立つきみに。
真実めざめることないその眼差しに
今朝も幾つもの意味無き影がよぎり、
それを見つめる僕の影もよぎる。
もしも
きみの眼差しが僕の姿を捕えたなら
あの、待ちに待ったひとことを
ようやくきみに贈ることが出来るのだ。
「はじめまして……」と。
少女は毎朝、其処に立っていた。
城前にある広い公園の中の小さな森から、少しはずれた大樹の根方に。
濃い緑の葉は空を見上げる少女の額にまだらの影を作り、彼女の足元には白い小犬がまとわりついている。
小犬といっても元々小型犬なので、多分三才にはなっているはずだ。僕がまだ高校の部活の朝練でここを
走っていた頃から、あの犬は少女と一緒だったから。
犬が「小型犬」という種類であると同じく、少女もまた「少女」という種なのだろうか。
初めて見掛けてからの三年間、少女はずっと少女であり続けていた。あの大樹の根方では、
ずっと時が止まっているのかもしれない。
僕はゆったりとした駆け足で、公園の周回道路を通りすぎて行く。
ウインドブレーカーの擦れるかすかな音が、朝の静けさを乱す。
そして僕は、樹の下から公園の内側をじっと見つめている彼女に、軽く会釈する。
いつものように。
彼女の瞳の中を僕の影は駆け抜ける。
それは全く、雲の影や鳥の飛ぶ影と同じように、彼女にとっては何の感情も呼び起こさない自然現象。
いつものように……全くいつものように、僕は自分を風に飛ばされた枯葉か何かだと信じ込んで、
そのまま其処を駆け抜けて行く。枯葉は決して後ろを振り返ってはならない。
彼女の眼差しが僕を捕えることのない限り、僕はずっと枯葉でいるしかないのだ。
その朝、空気はいつもと違う香りがしていた。しんと凍み透る初秋の大気の中に、何か心を弾ませる
暖かな予兆が、確かにあった。その日、特に気分の焦っていた僕には、その予感はとても意外なものだった。
まだ夏と変わりなく鬱蒼と生い茂っている森の木々を縫い、僕は急いだ。
時刻は、いつものジョギングの時間よりかなり遅い。今朝に限って合わせたはずの目覚まし時計が鳴らなかったのだ。
夢の中でベルの音を聴いた気もするが、止めた憶えもないのにベルは一度きりしか鳴らなかった。
この時間ではたぶん彼女に会えない。
落胆と安堵の両方が僕の心に去来し、走りながら何故か一人苦笑していた。
僕のような人間が三年間も一人の人間に執着しているのは、自分でも可笑しい。
切実な願望も夢も無く、とりあえず予備校に通い大学合格を目指すだけが目的のような日々。
大学に受かったとしても何を学びたいという目当ても無い。かといって、何かやりたい仕事があるわけでもない。
僕は、死んでないから生きているというだけなのだ。
もし僕が今死んだとして、ずっと僕を憶えている人間など両親以外に誰が居るのだろう。
それなのに、ただ毎朝一目見掛けるだけの、何に対しても一切反応を示さない風変わりな少女に
僕は興味を引かれ、その存在だけが僕をこの世界につなぎ止めている。
公園の周回道に入ると、秋色に姿を変え始めた大樹が視界に飛び込んで来る。
その木陰には、もう誰もいない。溜め息がこぼれた。
不意に後ろから、何かが勢い良く僕の脚にぶつかってきた。
「おっと……」
倒れそうになった態勢を立て直し、斜めに体をよじってぶつかった者の正体を見る。
ワンワンワン、と甲高い声で吠えながら、あの真っ白な犬が僕の周りで跳ね回っていた。
「こら、やめなさいホワイト!」
くすくす笑いのような楽しげな声。シャボン玉が空で弾けるかすかな音のような。
少し安直に感じられる名前を呼びながら、少女は白い犬を両腕で抱え上げた。いつもの無反応の顔とは全く違う、
生き生きした瞳の色。風に揺れる巻毛の先にまで、生命が息づいている。これは、本当にあの少女なのか。
「どうもすみませんでした」
じゃれつく犬をあやしながら、少女は言った。清楚なブラウスとジャンバースカートの、どこにでも居そうな少女。
印象通りの美少女ではあったが、明るく微笑む表情は何処か平凡に映り、僕は彼女への興味を失っていた。
僕は急に気楽になり、彼女に話しかけた。
「今朝は散歩の時間、遅かったんですね」
少女の顔から笑顔が消え、瞳に困惑の色が広がっていった。
「……私を、知ってるの?」
呟くような声に包み込まれた怖れと悲しみ。 突然変わってしまった少女の様子に、僕は少したじろいだ。
「いや、知ってると言っても、いつもジョギング中にすれ違うだけで……」
「いつも……? もしかしたら、私、毎日あなたとすれ違ってるのかしら?」
少女は理解に苦しむようなことを言う。
三年間、毎朝僕が目の前を駆け抜けていたことに、あの無反応な眼差し通りに本当に気付いていなかったというのか。
それとも、風に散る木の葉を見るのと同じように、記憶に留める価値も無い出来事だったのか。
「僕は、三年間ずっときみの目の前を走り抜けていたのに、憶えてないの?」
かなり非難めいた口調なっていた。まずい、と感じるより先に、彼女の口元が歪み、震えた。
初めて僕の姿を真正面から見つめる瞳は、みるみるうちに涙で揺らぐ。
少女はぎゅっと目を閉じ、激しく何回も首を横に振った。
「あなたなんか知らない。憶えてないもの!」
叫んだ瞬間、睨むように僕を見たあと、少女は身をひるがえし森の中へ駆け去った。
僕は何があれほど彼女を怯えさせたのか判らず、呆然としたまま公園中を走り回った。
さっきの暖かな予感は、間違いだったのか。
少女のこぼした涙のきらめきが、心の奥を刺したまま、消えることなく光り続けていた。
その日の帰りは真夜中だった。珍しく高校時代の友人たちと飲みに行ったのだが、
酒に強い僕は酔っ払った友達を家まで送っていて遅くなってしまった。
友人の家から自宅まで、早朝のジョギングコースとほとんど同じ道程も、静かな夜の中では見慣れぬ景色に見える。
小さな城跡の石垣の影が、街灯に黒く浮かび上がっている。森の木々は星空の中に影絵のように立ち並び、
白い月は細い梢の尖塔の先でゆらゆらとバランスをとる。
ぼやけた月を見上げながら歩いていると、真っ暗な森の中にも、ほのかな白い光が揺れるのが見えた。
それは、にじむような軌跡を引いて、ゆっくりと近づいて来る。
僕は立ち止まり、白い光の源をみつめた。
あの少女だ。今は少女ひとりだけ、闇に溶け出すほど真白な裾の長い服を着て、
踊るように優雅な足取りで森の小路を歩いていた。少女は、いつもの何も映さない瞳をくるくると彷徨わせて、
小径を繰り返し左右に横切る。まるで氷の上を滑るように。
僕のほんの目の前まで来て、少女は立ち止まった。
大きな目を見開いているが、あまり驚いた様にもない表情で、僕をみつめる。
「やあ……」
今朝泣かせてしまったばかりなので、僕はためらいがちに声をかけた。
しかし、少女はただじっと焦点の合わない眼差しを僕に向け続けていた。そしてぽつりと尋ねた。
「あの……どこかで、私と会ったことない?」
僕は黙って頷いた。
「どうして森の中に居るのかわからないの」
と少女は言った。気がつくと森の中を歩いていて、なんだか気分が良いのでそのまま踊りながら歩いていたのだと言う。
「たぶん、こうして話してることも、何十分かしたら、きっと忘れてる。私って、何故だかわからないけど、
そうなっちゃうから。時どき何してるのか自分でも判らなくなって危ないからって、
普段は毎日決まったことだけするようにしてるんだけど……今日は一体どうしちゃったのかなあ」
肩を並べてゆっくりと歩きながら、彼女はさらりとそう言った。案外明るい表情で、ほとんど一方的に喋り続けていた。
「記憶喪失とは違うのよ。自分の名前も家も歳も、ちゃんと憶えてるもの」
「じゃあ、名前、教えてくれる?」
少し先を歩いていた少女は、月の光の中で振り向いた。
「美月……『美しい月』と書いて、みつき」
月を背にして光を纏った美月は、本当に月の化身のように見えた。
「あなたの名前は?」
美月が訊き返した。僕は、あまり自分の名前を口に出したくなかった。ちょっと自分のキャラクターじゃない名前だから。
「僕? 僕の名前は明。『明るい』のあきら。平凡な名前だろう」
「ううん、いい名前だと思う。『明るい明日の明くん』なんてね。いいじゃない」
美月は僕に向かってにっこり笑った。初めて見せる、満面の笑顔。
だが、それは長くは続かなかった。突然、美月は眉をしかめ、涙をこぼした。
「明日があるなんて、羨ましいわ。私、昨日のこと何も憶えてない。今日のことも、憶えられない。
……だから永遠に明日なんて来ない。何も憶えてないなんて……この三年間、生きてないのと同じだわ」
美月は思いを吐き出し、両手で顔をおおった。絞るような低い泣き声と小さく震える肩。
僕は思わずその肩をつかまえて、言った。
「生きてないなんて、そんなわけないじゃないか。僕は三年間ずっと、きみを見てたんだ。
きみが何も憶えてなくても、僕がきみを憶えている。絶対に忘れたりしない。
僕はきみを、いつまでも憶えている」
美月は、震えながら顔を上げた。彼女の瞳の中に、僕の姿が映っている。
いつも僕が望んでいたように、僕は二度と逃げ出せない眼差しの檻の中に、しっかりと捕われていた。
「ありがとう。とても、うれしい……」
美月はそう呟き、僕の胸に自分の額をくっつけて、体をもたせかけた。
「ごめんね……。私、明日にはたぶんもう、今のことも、あなたのことも忘れてる」
声が胸に響く。華奢な肩に置いていた両手を、そっと背中まで回した。
少女の身体は冷たく、まるで壊れもののようで、僕はそれ以上腕に力を込めることができない。
けれど、薄紙一枚分の空気を介しても鼓動は伝わる。
別々の拍を打つ二つの鼓動を、新しい一つのリズムとして、胸に響かせる。
「忘れたくないのに……」
美月が、僕の背にきつく腕を回した。僕も想いのままに、彼女を抱き締めた。
「忘れても構わないよ。もう一度、また最初から出会えばいい。何度でもきっと、僕らは出会える……」
月明かりの下で、僕らは長いこと抱き締め合った。
互いに触れている間は、決して忘れることなど無いのだと信じて。
朝、公園の周回道路をジョギングするのが、僕の日課だ。白い息を散らして、今日も僕は森を抜けて走る。
すっかり葉の色を変えた公園一の大樹の下で、今朝も少女が白い犬と遊んでいる。
樹の下の少女を横目で見ながら、たるんだ身体に似合わないスポーツウエア姿のおばさんたちが、
僕とすれ違って行く。ほとんど歩くような速度で、僕の耳元に世間話の風を吹きつけながら。
「ねえ、今朝も来てるわよ、あの子」
「ほんとに可哀想よねえ。新しい記憶が全然出来ない病気なんですって」
「あの子、今十七だって言うけど十四までのことしか思い出せないって言うじゃない」
「そうそう、医療ミスで脳のどこかが、どうにかなっちゃったんだそうよ」
「じゃあ、学校にも行けないし、将来結婚も出来ないんじゃない? お見合いしても相手の顔が憶えられないんじゃあねえ」
僕は頭を左右に何回も振り、走る速度を増し、無遠慮な言葉たちを追い払った。
そして、彼女の立つ樹の手前で速度を落とし、ゆっくりと向きを変えた。
彼女の……美月についての事実がどんなものであろうと、僕にはそんなこと関係ない。
僕が出来ることは、たった一つ。たとえ美月が全く僕を憶えていなくても、僕は何度でも何度でも、彼女と出会い続ける。
ホワイトが嬉しそうな声をあげ、僕の足元にまとわりついてきた。僕は小犬を抱き上げ、美月の正面に立ち、微笑む。
「おはよう。とても可愛い犬だね」
美月はまじまじと僕の顔を見つめ、少し首を傾げて言った。
「あの…私たち、どこかで会ったことない?」 END